
別府八幡宮
別府八幡宮について
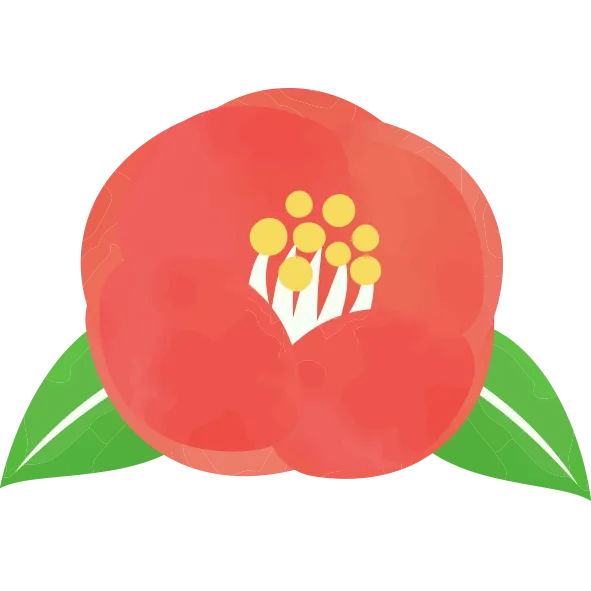
御由緒
当社は神護景雲四年(西暦770年)、和気清麻呂公よって豊前国(現在の大分県)の宇佐神宮より勧請されたことを創建の始めとしています。
僧道鏡の企てを阻止した宇佐神宮神託事件の折、野望を挫かれ憤激した道鏡により大隅国(現在の鹿児島県)へ流されていた和気清麻呂公は、道鏡の失脚後罪を解かれ勅命を受け京に召還されることとなります。
しかし海路帰京の途中、清麻呂公の船は嵐に遭ったが為にこれを避けて有帆の入り江(当時有帆の地は海に面していた)に船を寄せ、この地にて宇佐神宮の御霊代の御幣を松の木に掛け八幡神に祈ったところ、たちまちのうちに嵐は鎮まったといわれています。
そこで清麻呂公は「我今ここに八幡宇佐宮を勧請奉る。依りてこの郷の神とせよ」と仰せられ、御神威に驚嘆した民衆により社が建立されたとされています。
爾来千二五十年以上の歴史を有する古社であり、古来より、厚東・大内・毛利氏の崇敬篤く、厚東氏は代々の祈願所として社領を寄進し社殿を改築しました。
大内弘世は永和二年(1376年)本殿を造営しており、現在本殿西側にある旧本殿がこの建物であると伝えられています。
その後も寛文八年(1668年)に榎本就時は社殿を修復、現本殿東側にある旧拝殿は天保八年(1837年)毛利氏により改築されています。
明治十三年(1879年)には現本殿を造営し、昭和五十七年(1982年)に現在の幣殿・拝殿を改築し、近郷に誇る壮麗な社殿を整備し、今日に至ります。

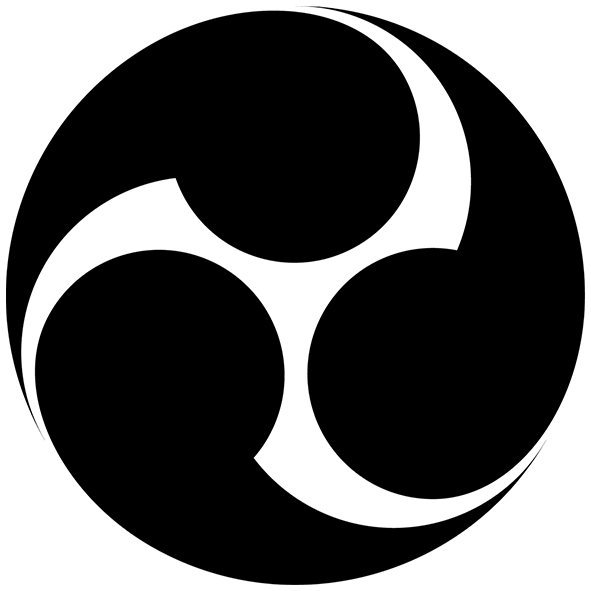
御祭神
応神天皇
誉田別尊(ほんだわけのみこと)仲哀天皇
帯中津日子命(たらしなかつひこのみこと)神功皇后
息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)多紀理毘売命 (たきりひめのみこと)
多岐都毘売命 (たぎつひめのみこと)
市杵島毘売命 (いちきしまひめのみこと)
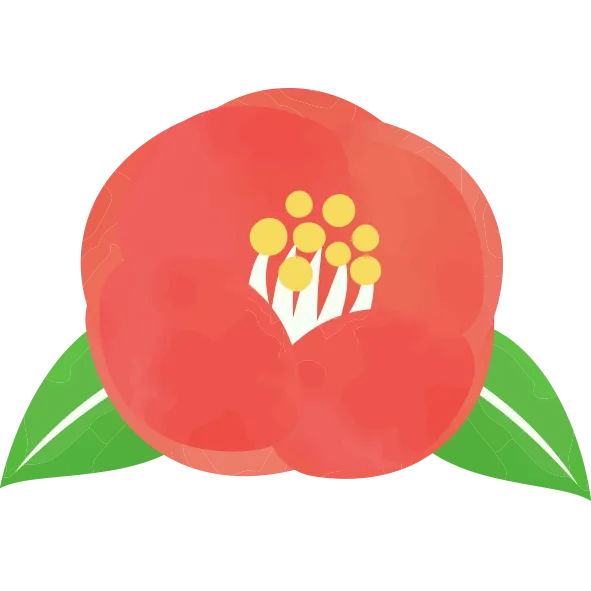
有帆雅楽会
有帆雅楽会は、当宮の神職を中心に活動を行っている雅楽会です。当宮の神職が指導をさせていただきますが、
本人もまだまだ未熟ものですので会員の皆様と共に研鑽を積んでいきたいと思っております。
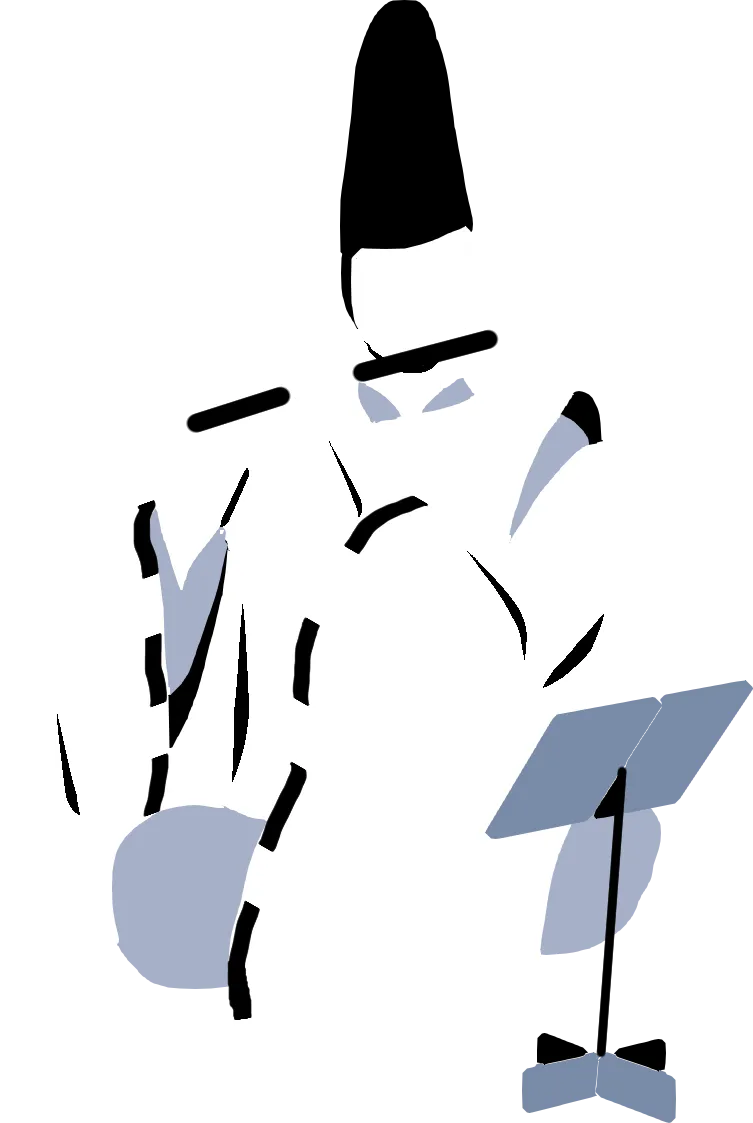
稽古日時
第1・第3水曜日 18:30~20:00
※初心者の方は一般のお稽古終了後、20:00~21:00までのお稽古となります
※お稽古日は急遽変更になることがありますので、見学等をご希望の方は事前に当宮までお問合せください
12月~2月中旬までは社務繁忙の為、お休みとなります。
-
● 会費・受講料等は無料ですが、会場使用料として毎回百円ほどお納めいただいております。
-
● 見学・楽器体験の参加等も大歓迎です。(※事前にご連絡いただけますと幸いです。)
稽古場所:別府八幡宮参集殿
お問い合わせ:別府八幡宮社務所 (電話:0836-84-0459)

